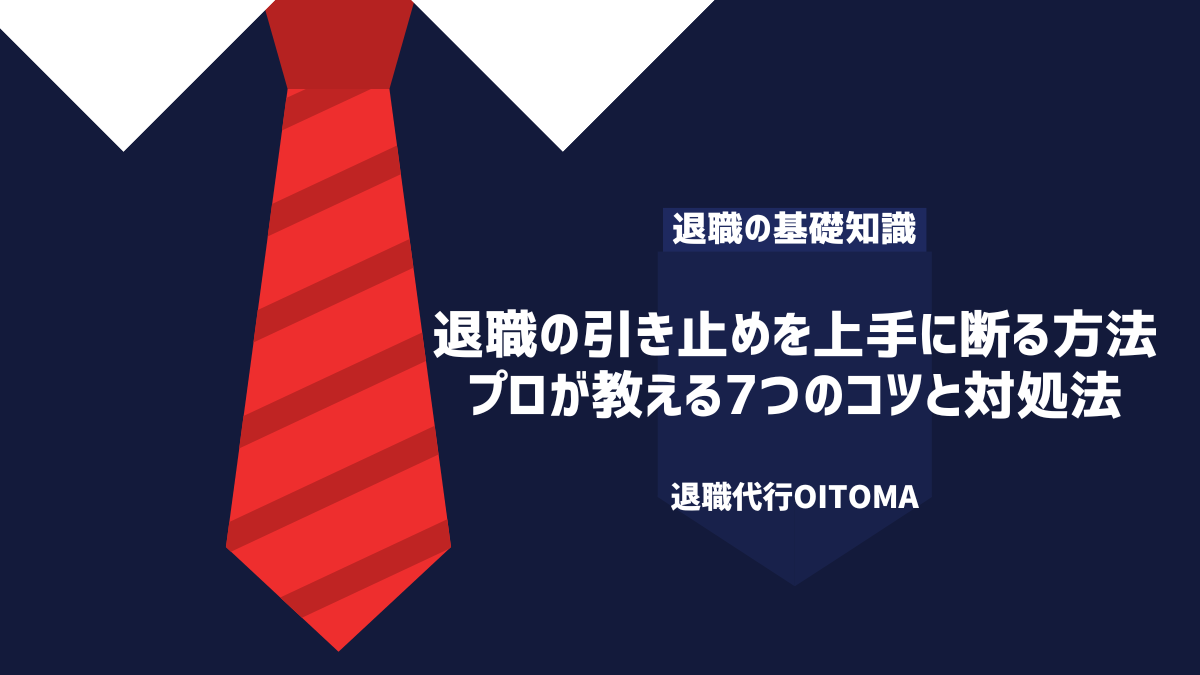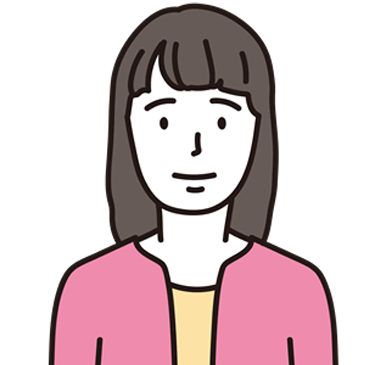 Kさん
Kさん
 Uさん
Uさん
退職を自分で伝えたのに、会社側に引き止められて辞められない方は実は多いです。
今回は、会社側に引き止められた際の対応方法や退職代行を利用するとどうなのかについて解説させて頂きます。
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
- なぜ退職を伝えても引き止められるのか
- 引き止められるかもと思った時の準備すべきこと
- 引き止めに合わない「退職意思」の伝え方
- よくある引き止めのパターン
- 引き留めを断ることは法律的に問題ないのか
退職の引き止めが行われる理由
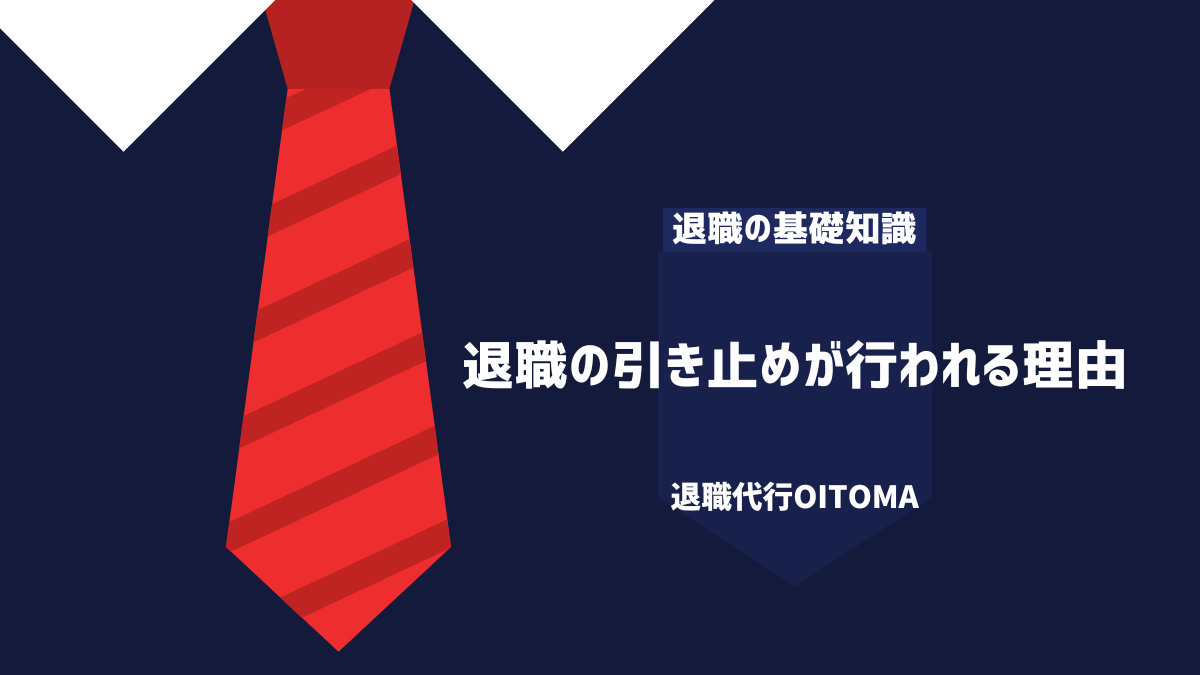
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
退職の意思を自分で伝えても退社を認めてもらえないことは多々あります。
これは、会社側の事情と上司の心理が複雑に絡まり発生しています。
それぞれの内容をより詳しくご紹介していきましょう!
理由①会社側の事情
優秀な人材や業務に精通した従業員の流出は大きな損失となります。これらの人材の退社は、会社の運営に直接的な影響を与える可能性があります。
また、人材の採用や育成にはコストと時間がかかるため、既存の社員を引き止めることで、これらのコストを抑えようとする意図もあります。
さらに、他の従業員への影響も考慮されます。一人の退職が連鎖的な退職を引き起こす「退職ドミノ」を防ぐため、会社は積極的に引き止めを行うことがあります。
理由②上司の心理
一方、上司の心理としては、チームの一員を失うことへの不安や、自身の管理能力を問われることへの懸念、個人的な感情などが引き止めの要因となることがあります。
また、長年一緒に働いてきた仲間としての情緒的な側面も無視できません。
上司は、単に業務上の関係だけでなく、人間関係の観点からも引き止めを行うことがあります。
- 会社側は、会社の運営の問題や人材育成へのコストや時間の問題が理由になることが多い
- 上司は、個人的な感情や人間関係的な視点が理由になることが多い
このような要因で退職の意思を伝えても引き止められることがあります。
次のセクションでは、引き止められても断る為の事前準備について解説していきます!
退職の引き止めを断るための事前準備
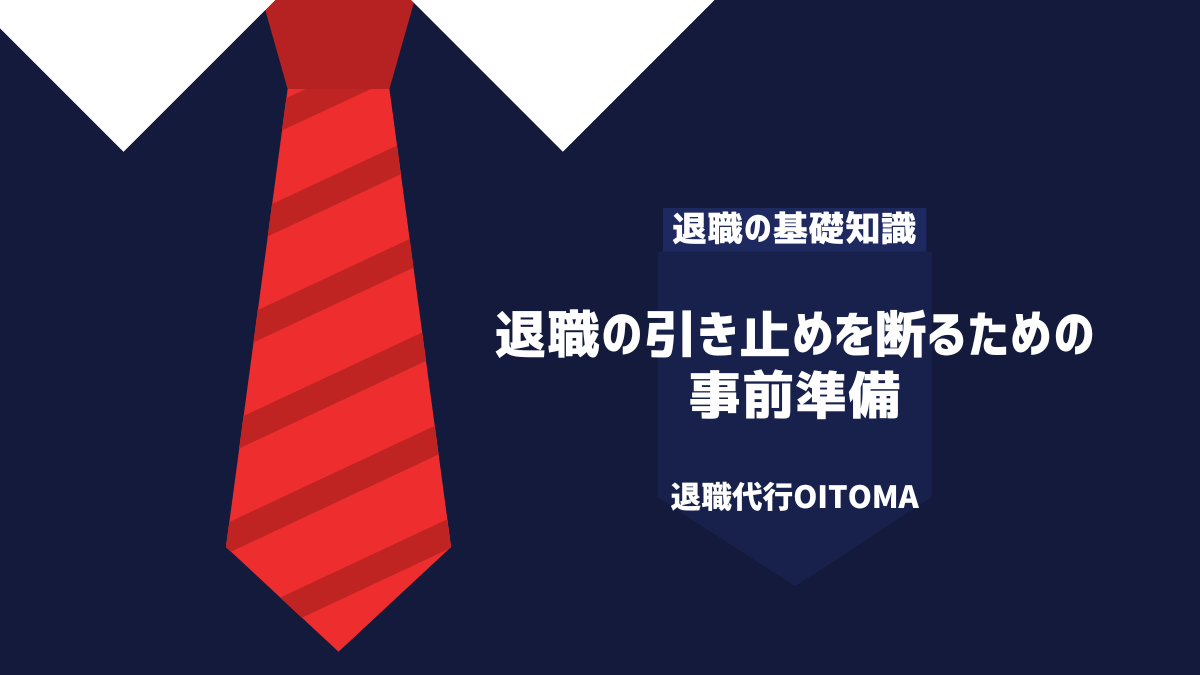
退職の引き止めを上手に断るためには、事前の準備が不可欠です。
しっかりと退職する為にも、次にあげることを予め準備しておきましょう!
準備①退職理由を整理する
なぜ退職を決意したのか、現在の職場のどのような点に不満があるのか、または新しい環境に何を期待しているのかを、具体的に言語化します。
準備②退職後のプランを明確化する
新しい職場が決まっている場合は、その職場でどのようなキャリアを築いていくのか、どのようなスキルを身につけたいのかを明確にします。
転職先が未定の場合でも、どのような業界や職種を目指しているのか、そのために必要な準備は何かを整理しておきましょう。
準備③生活費などの財政面の準備を行なう
退職に伴う収入の変化や、転職活動期間中の生活費などを考慮し、必要に応じて貯蓄を増やすなどの対策を講じておくことが大切です。
準備④引き継ぎの計画を立てる
どの業務を誰に引き継ぐのか、どのくらいの期間が必要かなどを事前に考えておくことで、退職の申し出の際にも具体的な提案ができ、会社側の不安を軽減することができます。
- 退職理由の明確化や退職後のプランの明確化を行なう
- 生活費などの財政面の準備や引き継ぎなどの計画立てを行なう
このような準備を整えることで、退職の引き止めに遭遇しても、自信を持って対応することができます。
また、これらの準備は、自分自身の決断を再確認し、新しいステージへの移行をスムーズにするためにも役立ちます。
プロが教える7つのコツ
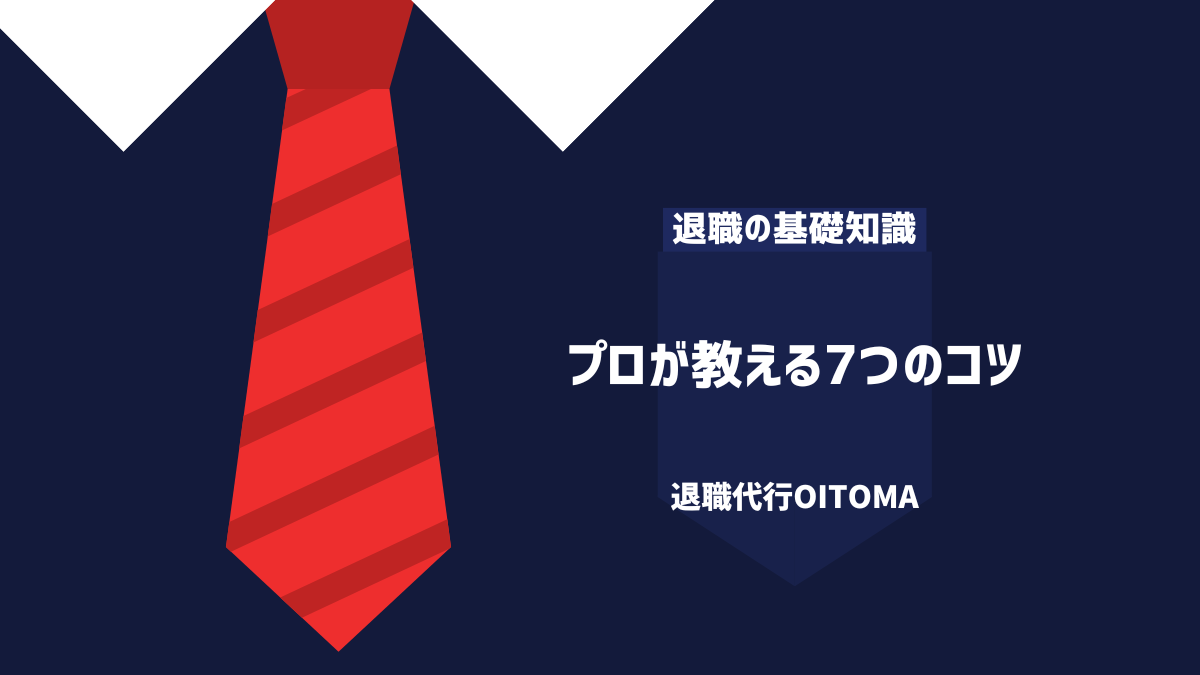
コツ①冷静さを保つ
感情的になってしまうと、後悔するような発言をしてしまったり、相手の感情を必要以上に刺激してしまう可能性があります。
また、相手の言葉に即座に反応するのではなく、一呼吸置いて考える時間を作ることも大切です。
「少し考えさせてください」と言って、その場で即答を避けることも一つの方法です。
冷静さを保つことで、相手の提案や意見を客観的に評価し、適切な対応を取ることができます。
コツ②明確かつ簡潔に伝える
曖昧な表現や遠回しな言い方は、相手に誤解を与えたり、さらなる引き止めの機会を作る可能性があります。
「私は退職を決意しました」というシンプルな表現から始め、必要最小限の情報を追加していきましょう。
退職理由を説明する際も、詳細な個人的事情や会社への不満を長々と述べるのは避けましょう。
代わりに、「キャリアの方向性を変えたい」「新しい挑戦がしたい」などの前向きな理由を伝えることが効果的です。
コツ③感謝の気持ちを表現する
会社や上司、同僚への感謝を伝えることで、退職という負の印象を和らげ、良好な関係を維持することができます。
具体的には、「これまでの経験は私にとって非常に貴重なものでした」などの表現を使うことができます。
ただし、過度に感情的にならないよう注意しましょう。
コツ④決意の固さを示す
「十分に考えた上での決断です」「この決定は覆りません」などの表現を使うことで、再考の余地がないことを伝えます。
ただし、強すぎる表現や攻撃的な態度は避けましょう。相手の立場を尊重しつつ、自分の意思を明確に伝えるバランスが重要です。
コツ⑤具体的な退職日を提示する
これにより、会社側も具体的な対応を検討しやすくなります。
法定の退職予告期間(通常は2週間)を考慮しつつ、できるだけ会社側に配慮した日程を提案しましょう。
例えば、「1ヶ月後の○月○日を退職日とさせていただきたいと考えています」といった具体的な提案をすることで、交渉の余地を残しつつ、自分の意思を明確に示すことができます。
コツ⑥引継ぎへの協力を申し出る
スムーズな退職のためには、引継ぎへの協力を自ら申し出ることが重要です。
「退職までの間、円滑な引継ぎに全力を尽くします」といった表現を使い、会社への配慮を示しましょう。
具体的な引継ぎ計画を提案できれば、なお良いでしょう。
これにより、会社側の不安を軽減し、退職の受け入れを促進することができます。
コツ⑦将来の関係性を大切にする
「今後も良好な関係を維持したいと考えています」といった表現を使うことで、退職が必ずしも関係の終わりではないことを示すことができます。
このような姿勢は、将来的なネットワーキングや再就職の可能性を開くだけでなく、現在の退職プロセスをより円滑にする効果もあります。
- 引き留めを断る時には冷静に
- 長々と話さず、明確・簡潔に
- 過度になり過ぎないように感謝を伝える
- 自らの意思の固さを、相手を尊重して伝える
- 具体的な退職日を明示する
- 引き継ぎへの協力姿勢を見せる
- 今後の関係性についてアピールする
このあたりをおさえておけば、相手を納得させることができるでしょう。
それでも引き止められる場合は、退職代行を利用することをオススメします。
よくある引き止めパターン5選
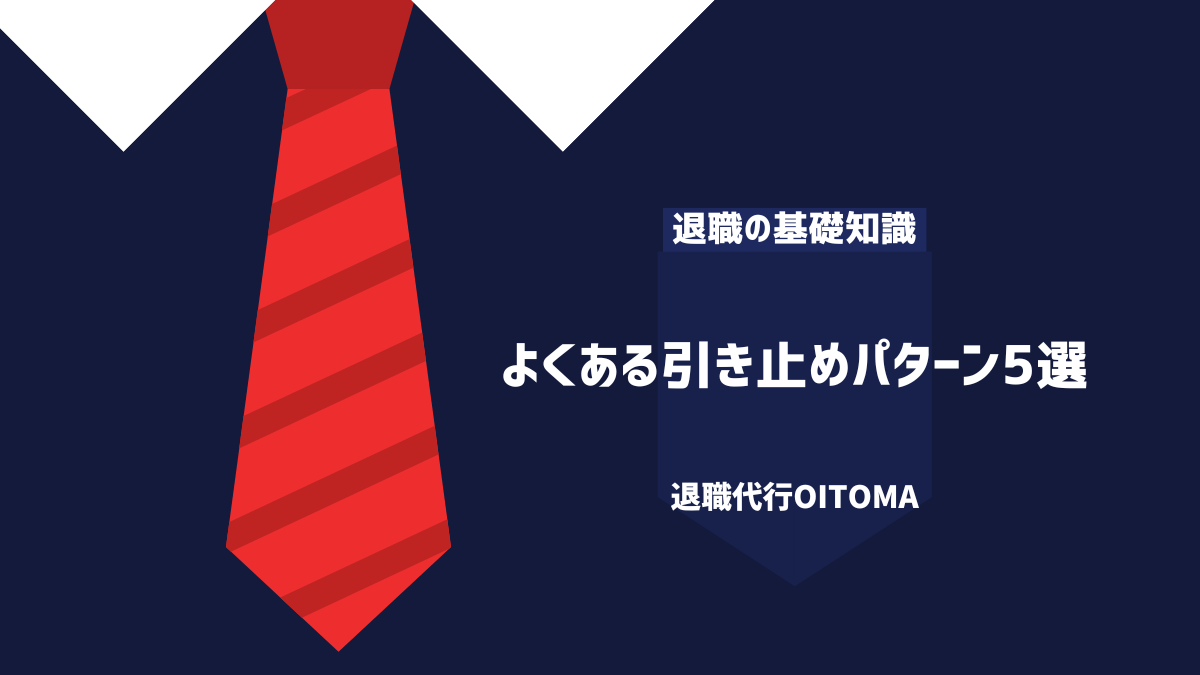
実際によくある引き止めパターンを知っておくことで、事前に準備が可能になります。
対処法を参考に、自分の状況に応じて修正をしていきましょう。
パターン①待遇改善の提案
給与アップ、昇進、新しい役割の提案など、様々な形で示される可能性があります。
このような提案に対しては、冷静に検討することが重要です。
対処法①退職理由を再確認する
単に待遇面の不満だけが理由ではない場合、これらの提案を受け入れても根本的な問題は解決しない可能性があります。
待遇ではない場合は、丁寧にお断りしましょう。
対処法②即座に受け入れない
「検討の時間をいただけますか」と伝え、冷静に考える時間を設けることが賢明です。
その間に、提案内容が本当に自分のキャリアプランと合致するかを慎重に評価します。
パターン②感情的な訴えかけ
「君がいなくなると困る」「チームのために残ってほしい」といった言葉で引き止めようとするケースです。
このような状況では、相手の気持ちを理解しつつも、自分の決断を曲げないことが重要です。
対処法:自分の考えを明確に伝える
相手の感情に共感や配慮をした上で、自分の立場や状況、考えを明確に伝えましょう。
パターン③罪悪感を利用する
「君が抜けると、残された社員の負担が増える」などといった言葉で、退職を思いとどまらせようとする手法です。
対処法:具体的な対策を提案する
引き継ぎの計画を伝える、在籍中に部下の育成を行なう等の具体的な提案を行ないましょう。
パターン④退職理由の追及
「具体的に何が不満だったのか」「改善の余地はないのか」といった質問を受ける可能性があります。
対処法:前向きな理由を伝える
詳細な個人的事情や会社への不満を述べると、改善する旨を伝えられ再度引き止められます。
「新しいキャリアへのチャレンジ」などの前向きな理由を簡潔に伝えることが効果的です。
パターン⑤再考を求める
「もう一度よく考えてみてほしい」「1週間後にもう一度話し合おう」といった形で、再考を求められることもあります。
対処法:毅然とした態度を取る
相手の立場を尊重し、丁寧な言葉遣いを心がけつつも、自分の意思をしっかりと伝えきりましょう。
引き止めを断った後のフォローアップ
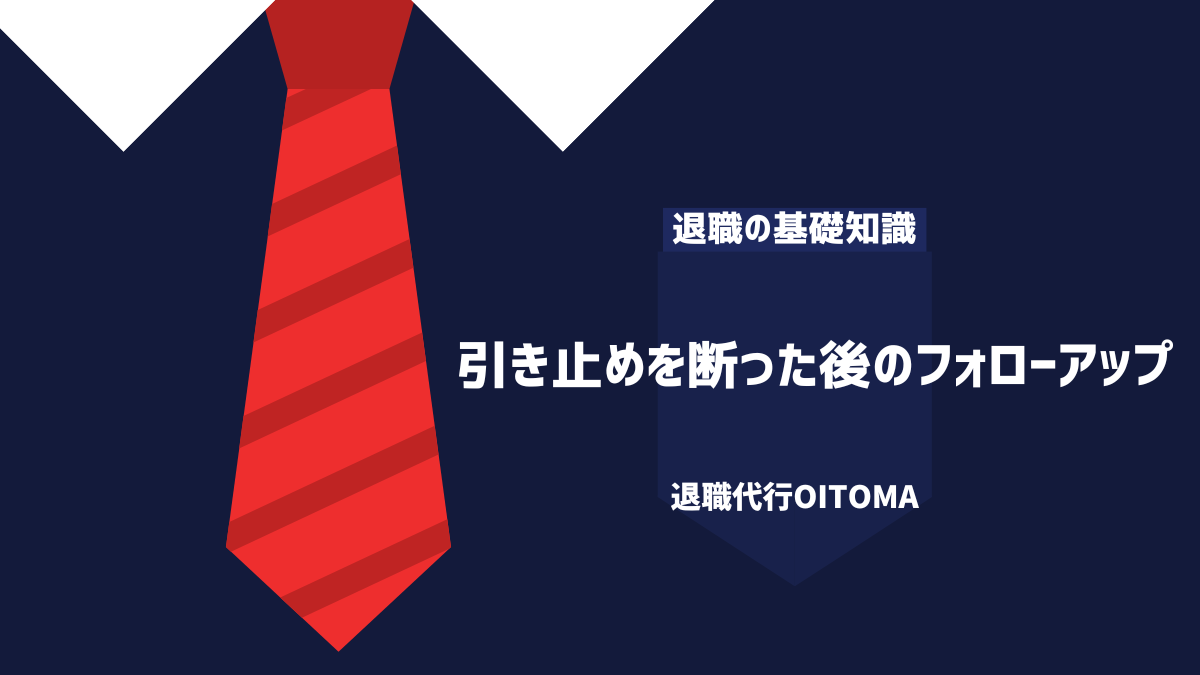
引き止めを断った後も、円滑な退職プロセスのためにはフォローアップが重要です。
フォローアップ①円滑に引き継ぎを行なう
まず、円滑な引き継ぎの実施に全力を尽くしましょう。
具体的な引継ぎ計画を立て、必要な文書やマニュアルの作成、後任者への説明など、できる限りの準備を整えます。
これにより、自分の退職後も業務に支障が出ないよう配慮することができます。
フォローアップ②今まで以上に仕事に取り組む
また、引継ぎ期間中は、通常以上に仕事に熱心に取り組むことが大切です。
退職が決まったからといって、モチベーションを下げたり、手を抜いたりすることは避けましょう。
最後まで責任を持って仕事に取り組む姿勢を示すことで、良好な関係を維持し、将来的な評判にも良い影響を与えることができます。
フォローアップ③上司や同僚に感謝を伝える
同僚や上司との関係を大切にし、感謝の気持ちを伝える機会を作りましょう。
例えば、小さな送別会を開いてもらったり、個別に挨拶回りをしたりすることで、良い思い出と共に退職することができます。
また、この期間を利用して、自分のネットワークを強化することも考えられます。
LinkedIn等のプロフェッショナルネットワークを更新し、今後の連絡先を交換するなど、将来的な関係維持のための準備をしておくと良いでしょう。
引き止めを断る際の法的な注意点
退職の際には、法的な側面にも注意を払う必要があります。
注意点①退職の意思表示は書面で行う
口頭での申し出だけでは、後々トラブルの原因になる可能性があります。
退職届には、退職の意思、希望退職日、自筆の署名を必ず記載します。
注意点②退職金や有給休暇の取り扱いを確認する
退職金の支給条件や金額、支給時期などを人事部門に確認しましょう。
有給休暇については、未消化分の取り扱いや退職日までの消化可能日数などを確認し、適切に処理することが重要です。
注意点③退職後の誓約事項を理解する
競業避止義務や機密保持義務などの誓約事項がある場合は、その内容と期間を十分に理解しておく必要があります。
不明な点があれば、人事部門や場合によっては弁護士に相談することをおすすめします。
それでも退職できなければ退職代行を利用しよう!
退職代行は、退職のプロです。
様々なお客様の退職をサポートしてきたノウハウをもとに、退職へとご案内します。
「何度も引き止められて…」
「引き止めが怖くて意思表示ができない…」
こんな悩みを解消いたします。
ご相談~退職まで即日対応可能な「退職代行OITOMA」までお気軽にご相談下さい!
[orange-light-cta]
まとめ
退職の引き止めを上手に断るためには、事前の準備と適切な対応が不可欠です。
本記事のポイントを押さえることで、退職の引き止めに適切に対応し、円滑な退職プロセスを実現することができます。
退職は新しいキャリアステージへの重要な一歩です。
引き止めに対して適切に対応することで、自信を持って次のステージに進むことができるでしょう。
また、退職後も良好な関係を維持することで、将来的なキャリアにも良い影響を与えることができます。
前向きな気持ちで退職を迎え、新たな挑戦に向けて歩み出しましょう。
よくある質問(FAQ)
- 退職の意思を伝えるベストなタイミングは?
-
一般的には、退職予定日の1ヶ月前程度が適切とされています。
ただし、会社の規定や自分の立場によって異なる場合もあるので、就業規則を確認しましょう。 - 退職理由を詳しく説明する必要はありますか?
-
詳細な説明は必要ありません。簡潔で前向きな理由を伝えるだけで十分です。
- 引き止めに遭って気が変わってしまいました。どうすべきですか?
-
慎重に考え直す時間を取りましょう。
ただし、一度退職の意思を伝えた後に翻意すると、信頼関係に影響を与える可能性があります。 - 退職後の競業避止義務はどの程度守る必要がありますか?
-
契約書に明記されている場合は、その内容に従う必要があります。不明な点は人事部門や弁護士に相談しましょう。
- 退職の引き止めを断った後、職場の雰囲気が悪くなりました。どうすべきですか?
-
プロフェッショナルな態度を保ち、最後まで責任を持って仕事に取り組みましょう。必要に応じて上司や人事部門に相談することも考えられます。