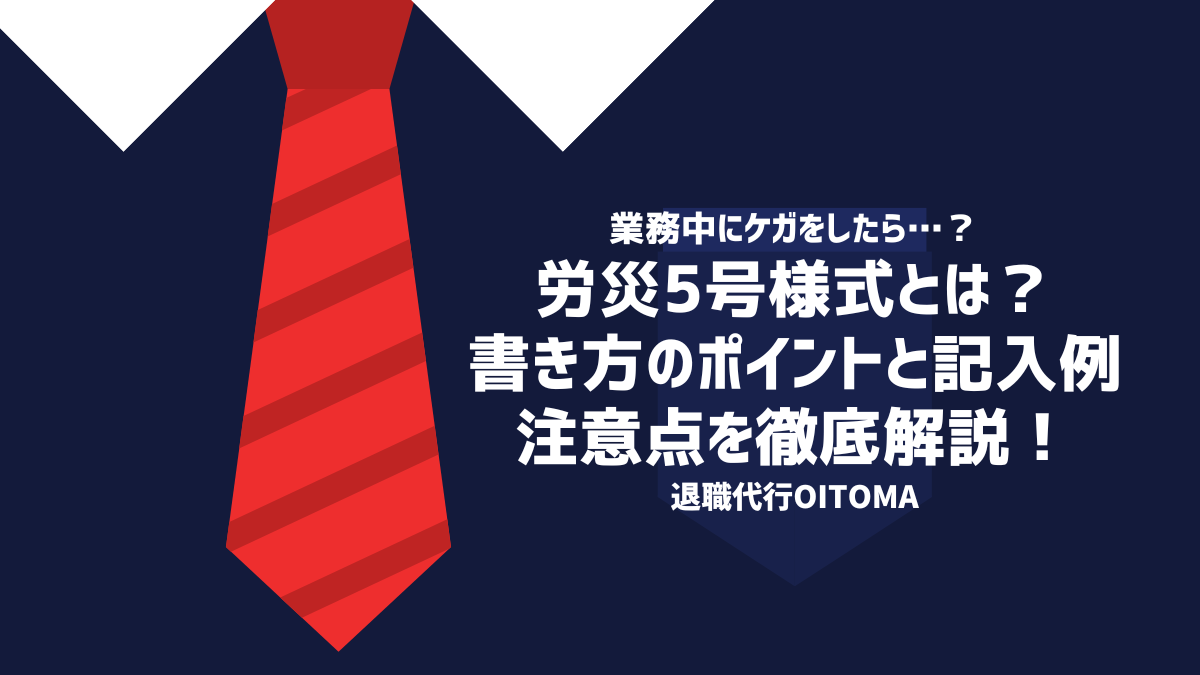はじめに
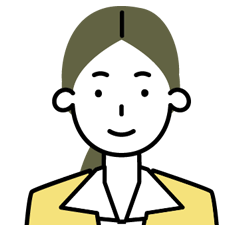 Aさん
Aさん
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
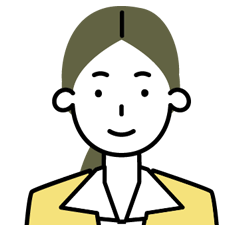 Aさん
Aさん
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
本記事では、労災5号様式の重要性を理解し、正確な記入方法を習得することを目的としています。初めて労災申請を行う方や、より詳細な情報を求める事業主の方々にとって、有益な情報源となるでしょう。労災5号様式の基本的な概要から具体的な記入例、申請時の注意点まで、幅広くカバーしています。
- 労災5号様式は、業務が原因の疾病である証明書
- 労災5号様式を提出するには、その他の書類の準備も必要になる
- 労災5号様式の記載での注意ポイントをおさえよう!
- 項目ごとの記入例をマネして、ミスなく正確な記入をしよう!
- 提出前に確認すべきポイントをおさえて、早期受給を目指そう!
労災5号様式とはどんな書類なの?
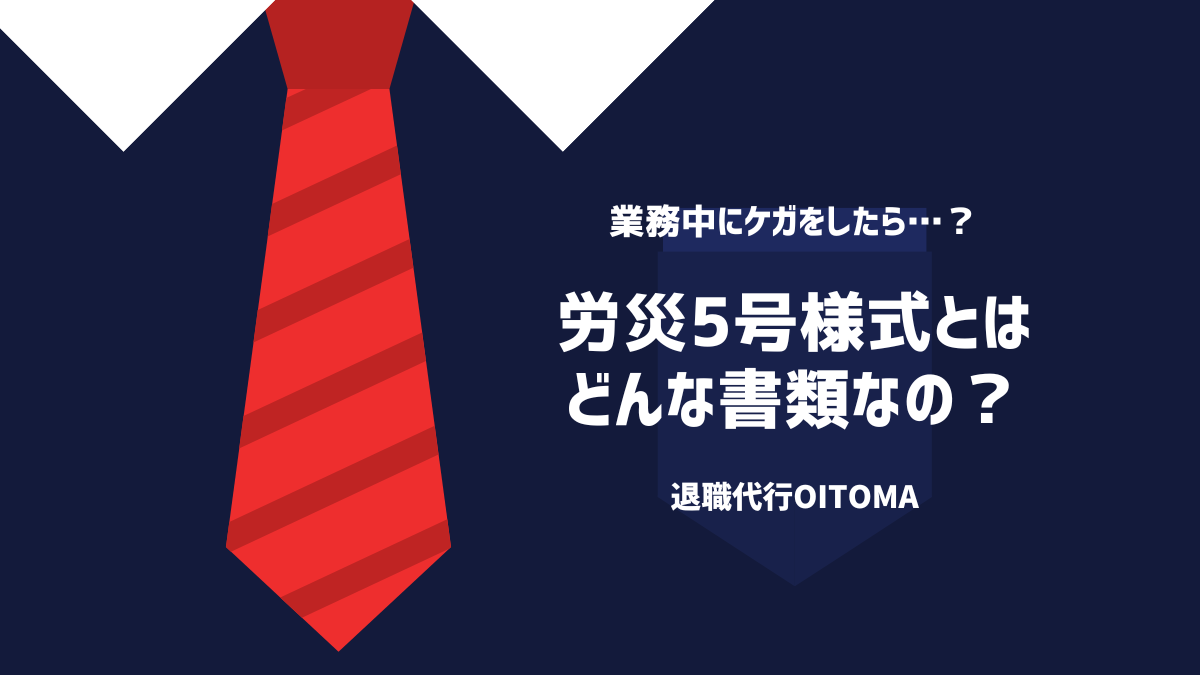
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
労災保険制度は、労働者が業務上の事由または通勤による災害によって負傷した場合に、適切な保護を行うことを目的としています。
この制度の下で、労災5号様式は「業務が原因の疾病である」ことを証明するために用いられます。
この様式を通じて、負傷の状況や治療の詳細、休業の有無などが労働基準監督署に報告されます。適切に記入された労災5号様式は、迅速かつ正確な補償給付の決定に寄与します。
具体的に労災5号様式を使用する場面としては、向上での作業中に機械に巻き込まれてケガをした場合や、オフィスで転倒して骨折した場合等があります。
労災5号様式の基本をおさえよう!
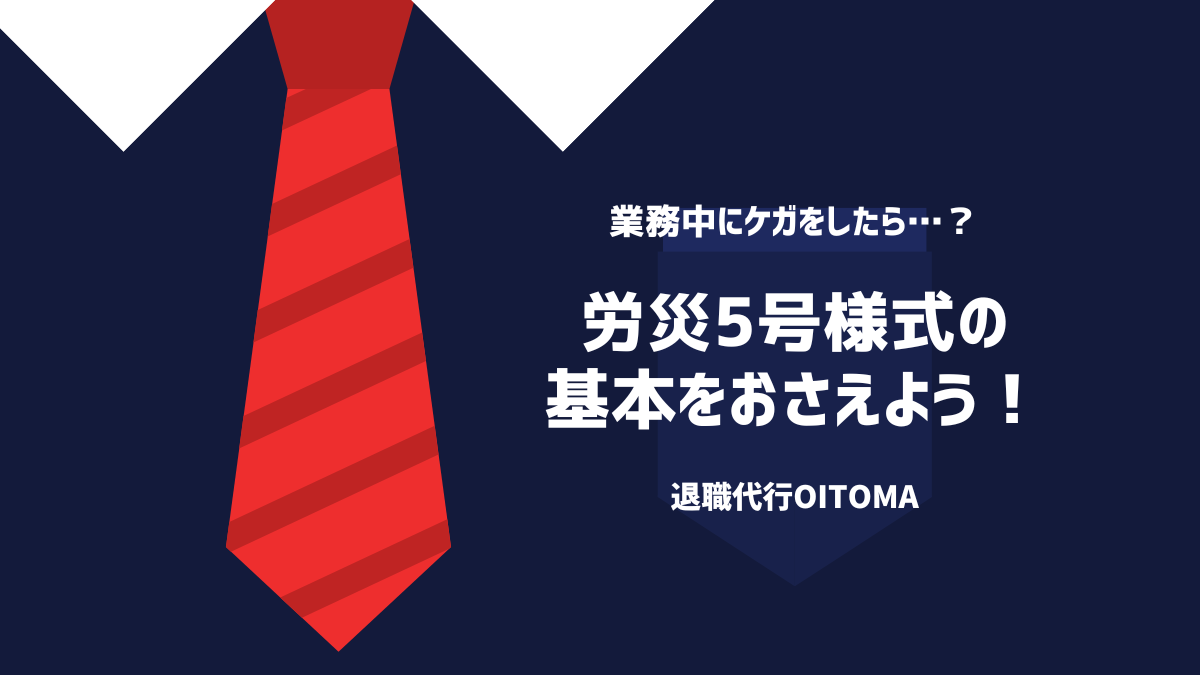
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
労災5号様式を適切に取り扱うためには、まずその基本的な情報を理解することが重要です。
様式の入手方法、必要な添付書類、提出先と期限について詳しく見ていきましょう。
基本①様式の入手方法
労災5号様式は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることができます。また、最寄りの労働基準監督署でも入手可能です。
オンラインでの入手が便利ですが、初めて申請する場合は労働基準監督署で直接受け取り、記入方法について助言を得ることをおすすめします。
基本②必要な添付書類
労災5号様式を提出する際には、他にも必要な書類があるので一緒に準備を進めましょう。
- 診療費請求書(様式第7号)
- 診療費明細書(様式第8号)
- 負傷の程度を証明する医師の診断書
- 事故証明書(通勤災害の場合)
これらの書類は、負傷の状況や治療の詳細を裏付けるものとして重要です。
特に医師の診断書は、労災認定の判断材料となるため、正確かつ詳細な記載が求められます。
基本③提出先と期限
労災5号様式は、事業場を管轄する労働基準監督署に提出します。
提出期限は、原則として負傷の日から2年以内とされていますが、できるだけ早期の提出が望ましいです。
適切な時期に正確な情報を記入した労災5号様式を提出することで、労災保険制度の恩恵を最大限に受けることができます。
労災5号様式を書く際に注意すべきポイント5選
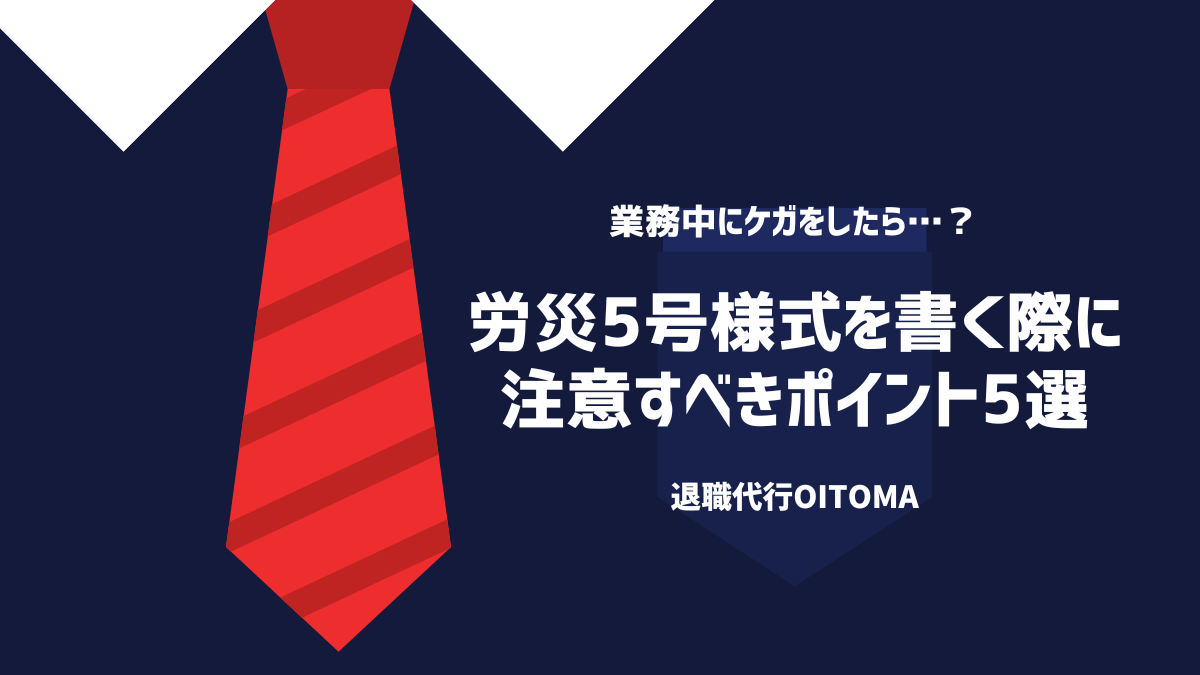
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
労災5号様式を正確に記入することは、スムーズな労災申請プロセスの鍵となります。
ここでは、主要な記入項目ごとにポイントを解説します。
ポイント①事業主・事業場に関する情報
この項目では、事業主の氏名や事業場の名称、所在地などを記入します。
正確な情報を記載することで、労働基準監督署が迅速に事業場を特定し、必要な調査を行うことができます。
- 事業場の名称は正式名称を使用する
- 所在地は番地まで正確に記入する
- 事業主印を忘れずに押印する
ポイント②負傷者に関する情報
負傷者の氏名、生年月日、住所などの基本情報に加え、職種や雇入年月日も記入します。
この情報は、労働者の就業状況を確認するために重要です。
- 氏名はフリガナも忘れずに記入する
- 職種は具体的に記載する(例:「営業職」ではなく「自動車部品販売営業」)
- 雇入年月日は正確に記載する(不明な場合は事業主に確認)
ポイント③災害発生状況の記入
この項目は労災認定の判断材料となるため、特に慎重に記入する必要があります。
発生日時、場所、災害の原因や状況を詳細かつ客観的に記述します。
- 日時は可能な限り正確に記載する(時刻まで記入)
- 発生場所は具体的に記載する(「工場内」ではなく「第2工場3階組立ライン」など)
- 災害の状況は第三者が理解できるよう明確に記述する
ポイント④医療機関に関する情報
治療を受けた医療機関の名称、所在地、初診年月日などを記入します。
複数の医療機関で治療を受けた場合は、すべての情報を記載することが重要です。
- 医療機関の正式名称を使用する
- 転院した場合はその経緯も簡潔に記載する
- 初診年月日は正確に記載する(医療機関に確認することをおすすめ)
ポイント⑤休業に関する情報
負傷により休業した場合、その期間や賃金支払状況を記入します。
この情報は休業補償給付の算定基礎となるため、正確さが求められます。
- 休業期間は暦日で記入する(土日祝日も含む)
- 休業中の賃金支払状況は具体的に記載する(全額支払、一部支払、未払いなど)
- 部分休業の場合はその旨を明記する
これらのポイントを押さえて労災5号様式を記入することで、適切な労災申請が可能となります。
各項目の詳細な記入例をマネしよう!
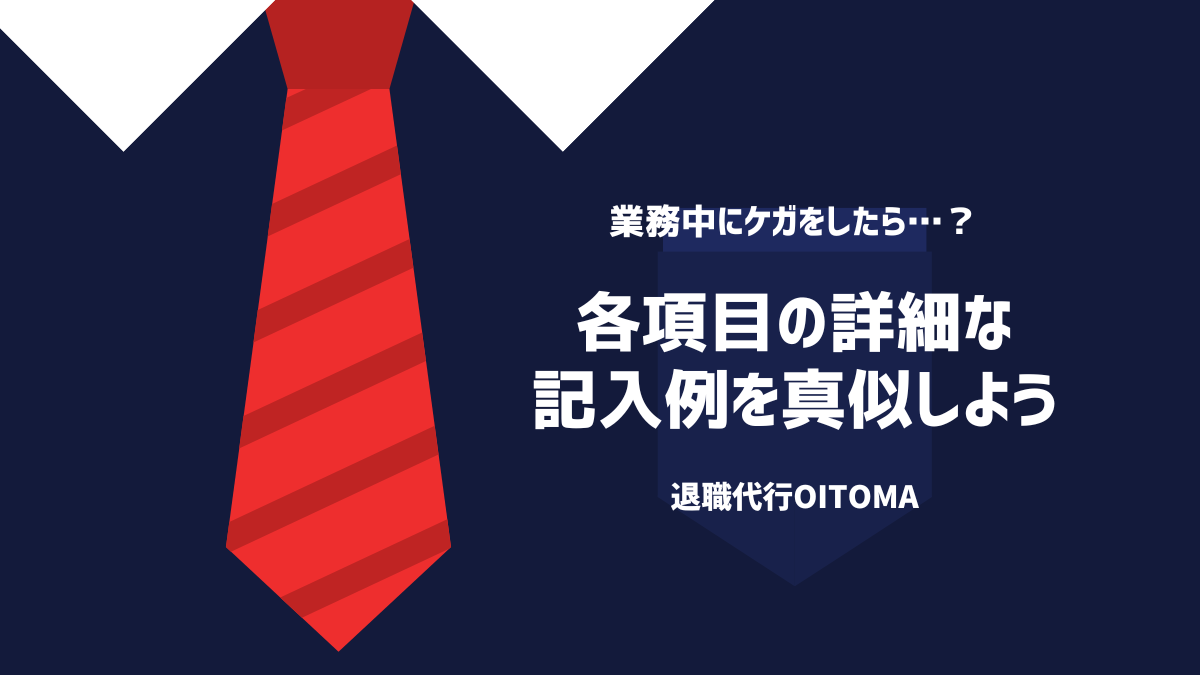
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
労災5号様式の各項目について、具体的な記入例を示しながら詳しく解説します。
これらの例を参考にすることで、より正確で分かりやすい申請書の作成が可能となります。
記入例①事業主・事業場情報の記入例
事業場の名称:株式会社山田製作所 東京工場
所在地:〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
事業主氏名:山田 太郎
この例では、正式な事業場名称と完全な所在地を記入しています。
事業主氏名は代表者の氏名を記入し、押印を忘れずに行います。
記入例②負傷者情報の記入例
氏名:鈴木 一郎(スズキ イチロウ)
生年月日:昭和60年4月1日
住所:〒200-0002 東京都新宿区新宿2-2-2
職種:機械組立工
雇入年月日:平成22年4月1日
負傷者の基本情報を漏れなく記入します。
職種は具体的な業務内容が分かるように記載し、雇入年月日は正確な日付を記入します。
記入例③災害発生状況の記入例
発生年月日:令和3年6月15日 午前10時30分頃
場所:東京工場 第2組立ライン
状況:
組立作業中、部品を運搬していた台車が足に接触し、右足首を負傷した。床が滑りやすく、急ブレーキをかけた際に制御を失ったことが原因と考えられる。
災害発生の状況を具体的かつ客観的に記述します。
発生時刻、場所、原因などを明確に記載し、第三者が状況を理解できるよう心がけます。
記入例④医療機関情報の記入例
診療機関の名称:新宿中央病院
所在地:〒300-0003 東京都新宿区西新宿3-3-3
初診年月日:令和3年6月15日
治療を受けた医療機関の情報を正確に記入します。
複数の医療機関で治療を受けた場合は、それぞれの情報を記載します。
記入例⑤休業情報の記入例
休業期間:令和3年6月16日から令和3年7月15日まで
休業中の賃金:6月分は全額支払、7月分は8割支払
休業期間を正確に記入し、休業中の賃金支払状況も具体的に記載します。
部分的な休業や段階的な職場復帰の場合は、その詳細も記入します。
申請時の注意すべきポイントをおさらい!
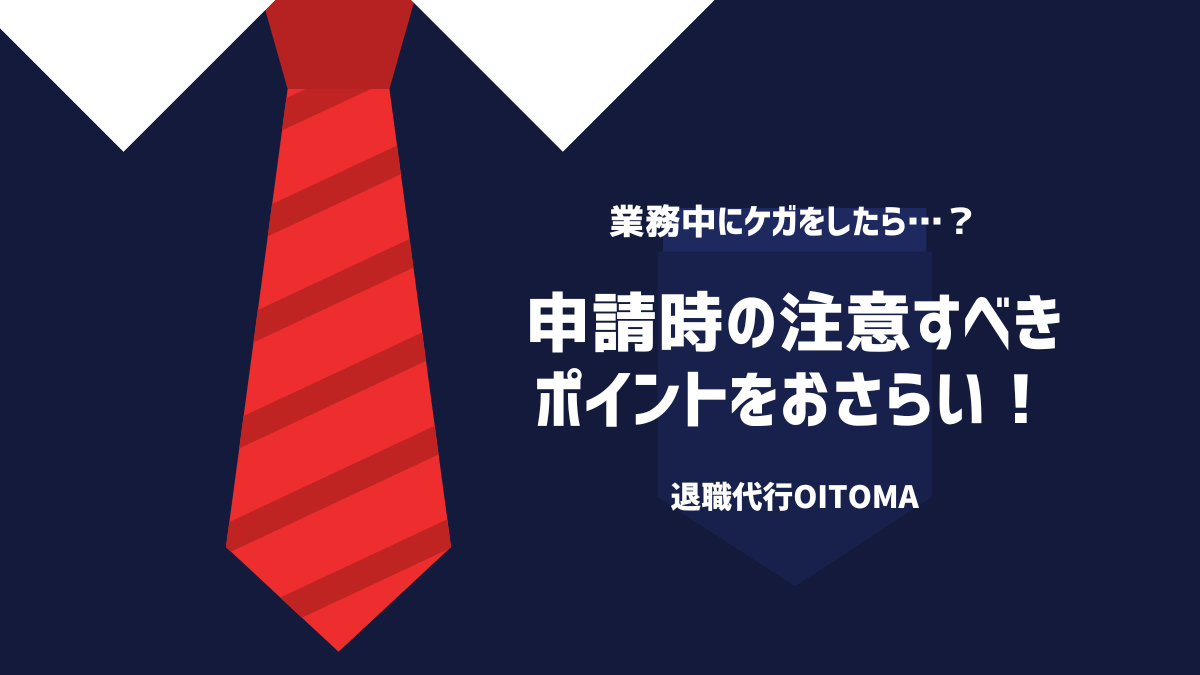
 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
労災5号様式の申請にあたっては、いくつかの重要な注意点があります。
これらを意識することで、申請書類の不備を防ぎ、スムーズな処理を促進することができます。
注意点①記入漏れや誤記に注意
労災5号様式の全ての項目を丁寧に確認し、記入漏れや誤記がないようにしましょう。
- 日付や数字の記入ミス
- フリガナの漏れ
- 押印忘れ
これらの小さなミスが、申請処理の遅延につながる可能性があります。
記入後は必ず第三者にチェックしてもらうことをおすすめします。
注意点②添付書類の確認
必要な添付書類が揃っているか、再度確認しましょう。
- 診療費請求書(様式第7号)
- 診療費明細書(様式第8号)
- 医師の診断書
- 事故証明書(通勤災害の場合)
これらの書類が不足していると、申請が受理されない可能性があります。
特に医師の診断書は重要で、負傷の程度や治療の必要性を明確に示す内容であることを確認してください。
注意点③提出期限の厳守
労災5号様式の提出期限は、原則として負傷の日から2年以内とされています。
しかし、できるだけ早く提出することが望ましいです。
- 迅速な補償給付の決定
- 記憶が新しいうちに正確な情報を記入できる
- 追加の書類や情報が必要な場合に対応しやすい
- 全て手続きは丸投げでOK
- 業界最安値で低価格で依頼できる
提出が遅れると、詳細な状況確認が難しくなり、結果として認定に時間がかかる可能性があります。
注意点④事実関係の正確な記載
労災5号様式には、事実に基づいた正確な情報を記入することが極めて重要です。
虚偽の記載は法律違反となる可能性があるだけでなく、労災認定にも悪影響を与えます。
- 災害発生状況は客観的事実に基づいて記述する
- 推測や憶測は避け、確認済みの情報のみを記入する
- 記憶が曖昧な部分は「約」や「頃」などの表現を使用する
正確な情報を提供することで、公平かつ適切な労災認定が可能となります。
よくある質問(FAQ)
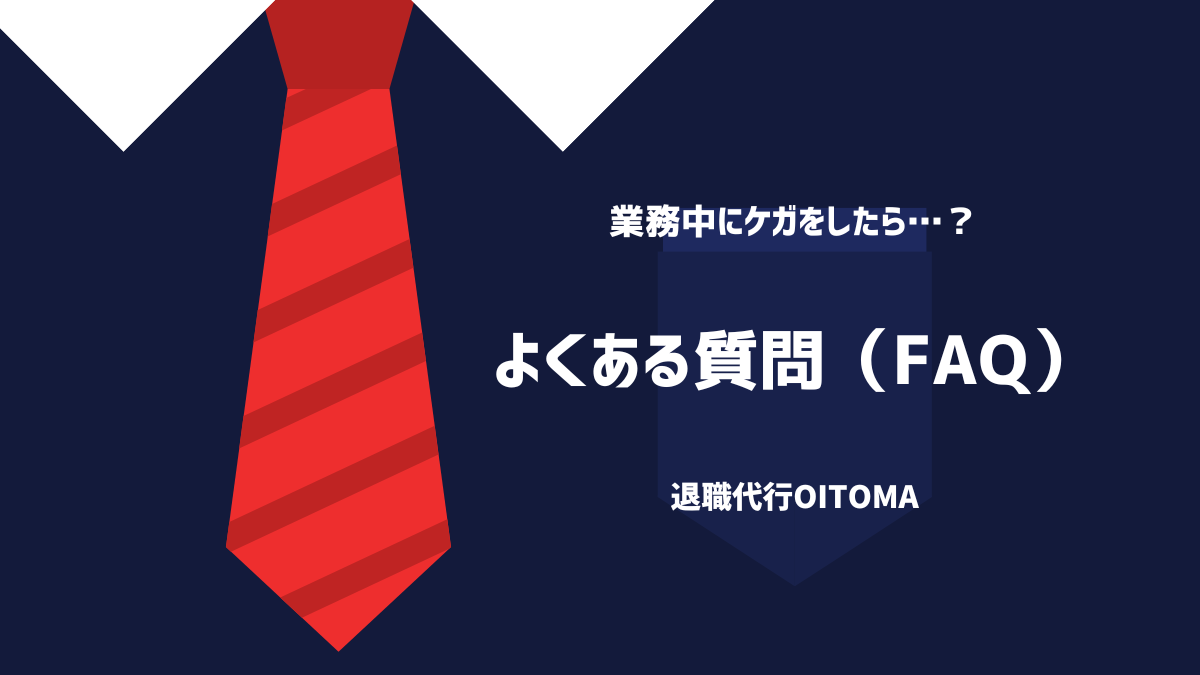
労災5号様式の申請に関して、多くの方が疑問や不安を抱えています。ここでは、よくある質問とその回答を紹介します。これらの情報は、申請プロセスをより円滑に進めるのに役立つでしょう。
記入ミスをした場合の対処法
- 労災5号様式に記入ミスをしてしまった場合、どうすればよいですか?
-
記入ミスに気づいた場合は、ミスのレベルに応じて修正をします。
1. 軽微な誤りの場合:二重線で消し、訂正印を押して正しい内容を記入します。
2. 大きな誤りや多数の訂正がある場合:新しい用紙に書き直すことをおすすめします。
3. 提出後に気づいた場合:速やかに労働基準監督署に連絡し、指示を仰ぎます。
正確な情報提供が重要なので、提出前に十分確認することが大切です。
複数の負傷がある場合の記入方法
- 一度の事故で複数の箇所を負傷した場合、どのように記入すればよいですか?
-
複数の負傷がある場合は、次の様に対応をします。
1. 「負傷又は疾病の部位及び状態」の欄に、すべての負傷箇所と状態を記入します。
2. スペースが足りない場合は、別紙を添付して詳細を記載します。
3. 各負傷の関連性や事故との因果関係を明確に説明します。
医師の診断書にも全ての負傷について記載されていることを確認し、添付することが重要です。
自賠責保険との関係
- 通勤中の交通事故で負傷した場合、自賠責保険と労災保険はどのように関係しますか?
-
通勤災害の場合、自賠責保険と労災保険の関係を解説します。
1. まず労災保険に申請を行います。
2. 労災認定された場合、労災保険から補償を受けます。
3. 自賠責保険からの支払いは、労災保険の給付額を差し引いた額となります。
労災5号様式の記入時には、自賠責保険の申請状況も記載するようにしましょう。両方の保険を適切に活用することで、十分な補償を受けることができます。
労災認定されなかった場合の対応
- 労災5号様式を提出したものの、労災認定されなかった場合はどうすればよいですか?
-
労災認定されなかった場合の対応は次の様に行います。
1. 不支給決定通知書を確認し、理由を把握します。
2. 不服がある場合は、決定から3か月以内に審査請求を行うことができます。
3. 審査請求の際は、新たな証拠や事実関係の詳細な説明を準備します。
4. 必要に応じて、労働組合や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。
認定されなかった理由を十分に理解し、必要な情報や証拠を補強して再申請することが重要です。
これらのFAQを参考にすることで、労災5号様式の申請に関する疑問点を解消し、より適切な対応が可能となります。不明点がある場合は、躊躇せず労働基準監督署や専門家に相談することをおすすめします。
本記事のまとめ
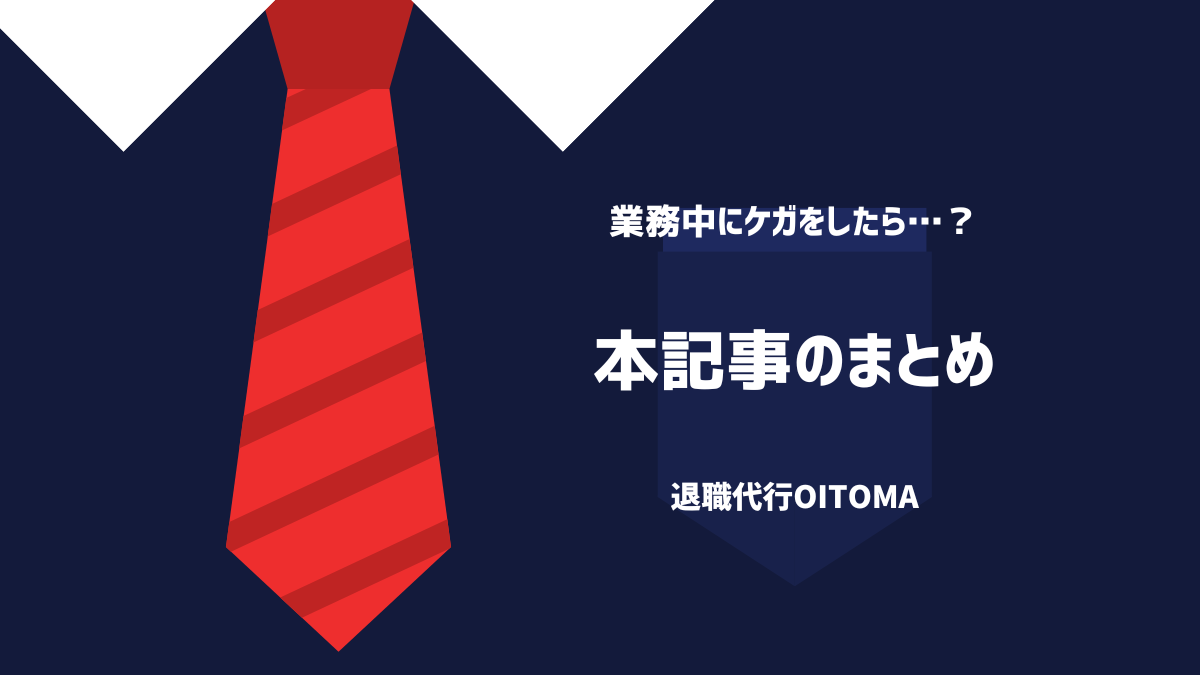
労災5号様式は、労働災害における療養補償給付請求の重要な書類です。
適切に記入し提出することで、円滑な労災認定プロセスと適切な補償を受けることができます。本記事で解説した主要なポイントを再確認しましょう。
- 労災5号様式の重要性と基本的な役割を理解する
- 様式の入手方法、必要な添付書類、提出先と期限を把握する
- 各項目の記入ポイントを押さえ、具体的な記入例を参考にする
- 申請時の注意点(記入漏れ、添付書類の確認、提出期限、事実関係の正確な記載)を意識する
不安や疑問がある場合は、労働基準監督署や専門家に相談することを躊躇せず、適切なサポートを受けながら申請プロセスを進めていくことをおすすめします。