 オイトマスタッフ
オイトマスタッフ
希望を胸に入社したはずが、現実とのギャップ・職場の人間関係・仕事内容のミスマッチなどに直面し、早くも退職を考える人は少なくありません。
そんな中で注目を集めているのが 「退職代行サービス」 です。
会社に直接言わずに退職できるという心理的な負担の軽減が評価され、利用者は年々増加しています。
しかし、新卒1年目という重要な時期に退職代行を使うことは本当に正しい選択なのでしょうか?
この記事では、
- 新卒1年目が退職を考える理由
-
退職代行のメリット・デメリット
-
代替案や注意点
を分かりやすく解説します。
退職代行サービスの概要
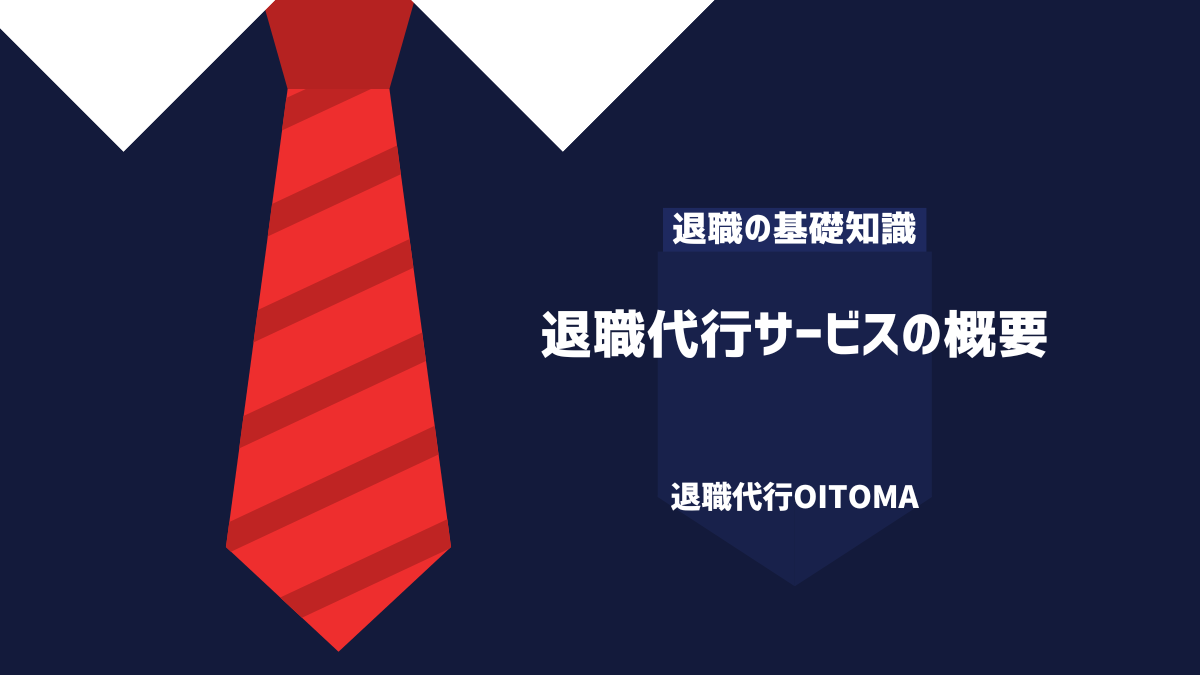
退職代行サービスの仕組み
退職代行サービスは、従業員に代わって会社側に退職の意思を伝え、必要な手続きを進めるサービスです。
利用者は直接会社とやり取りすることなく、心理的負担を軽減しながら退職できるのが大きな特徴です。
1.利用者が業者に連絡し、状況や希望を説明
2.業者が会社に連絡し、退職の意思を伝達
3.退職届の提出や社会保険の手続きなどを代行
4.一部の業者では、退職後の転職支援や労働トラブル解決のサポートもあり
主な退職代行業者
近年市場は急速に拡大し、多くの業者が参入しています。
- EXIT:業界最大手で知名度が高い
- 退職代行Jobs:労働組合提携で安心、即日対応
- 退職代行ガーディアン:モラハラ対応に強い
OITOMA
- 料金は24,000円のみ
-
LINEで即日対応
-
弁護士監修で安心
-
アフターフォロー(転職サポートなど)が充実
業者ごとに特徴が異なるため、自分の状況に合ったサービスを選ぶことが大切です。
退職代行サービスの料金相場
料金は依頼内容によって幅があります。一般的な相場は以下の通りです:
-
基本プラン:3万〜5万円(退職意思の伝達や基本的手続き)
-
即日対応プラン:5万〜8万円(緊急案件に対応)
-
法的支援付きプラン:10万〜20万円(退職金交渉や労働問題に対応)
一見高額に感じるかもしれませんが、心理的負担の軽減・時間の節約・トラブル回避を考えると利用価値があると感じる人も多いです。
新卒1年目が退職を考える理由
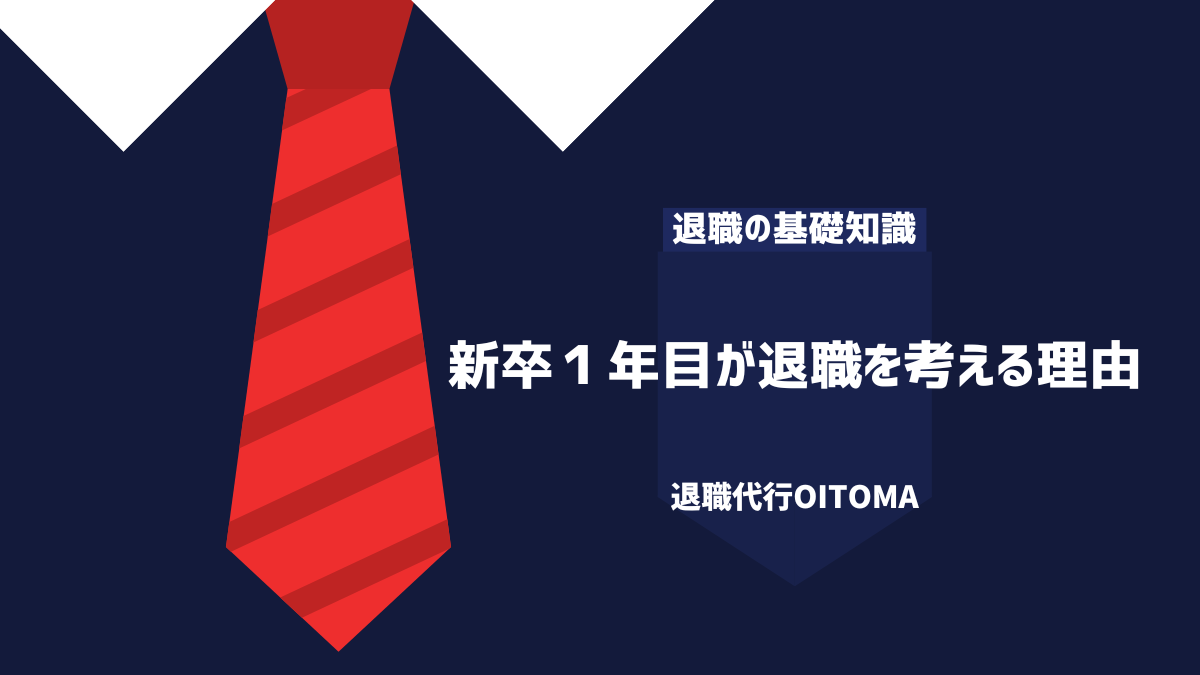
ミスマッチング
新卒1年目で退職を考える最も一般的な理由が、仕事や環境とのミスマッチです。
就職活動時に描いていたイメージと現実が大きく異なるケースは少なくありません。
-
期待していたクリエイティブな仕事がなく、単調な事務作業が中心
-
成長できると思っていたのに、スキルアップの機会が乏しい
-
会社の文化や価値観が合わない(長時間労働や厳しい上下関係 など)
このようなギャップに直面し、戸惑いを覚える新入社員は多いです。
パワハラ・モラハラ
残念ながら、職場でのハラスメントも大きな退職理由の一つです。
-
上司や先輩からの過度な叱責や理不尽な要求
-
人格を否定するような言動
-
新人という立場から、声を上げにくく我慢を強いられる状況
このような環境は、心身の健康を著しく損なう危険があります。
体調不良・メンタルヘルスの問題
新卒1年目は社会人としての経験が浅く、ストレスや負担を抱え込みやすい時期です。
その結果、次のような症状で退職を考える人もいます。
-
慢性的な疲労、不眠、食欲不振などの身体症状
-
うつ病や不安障害といったメンタルの不調
-
限界を超えて働き、心身のバランスを崩す
特に長時間労働や過度なストレスが続くと、健康を優先して退職を選ばざるを得ない状況に追い込まれるのです。
キャリアプランの変更
入社後にキャリアを見直し、現在の仕事が将来の目標達成に適していないと感じることもあります。
例えば、別の業界や職種に興味を持ち転職を考え始めるケースです。また、
-
大学や専門学校で学んだ専門知識を活かしたい
-
起業や海外就職といった新たなキャリアパスを模索したい
と考えることもあります。
このような場合、今の会社に留まることがキャリア形成の妨げになると判断し、早期退職を選ぶ新卒社員もいます。
こうした理由から、新卒1年目という早い段階で退職を検討する若者は増加傾向にあります。
ただし、退職の決断は慎重さが必要であり、その過程で退職代行サービスを選択肢に入れる人も少なくありません。
新卒1年目が退職代行を利用するメリット
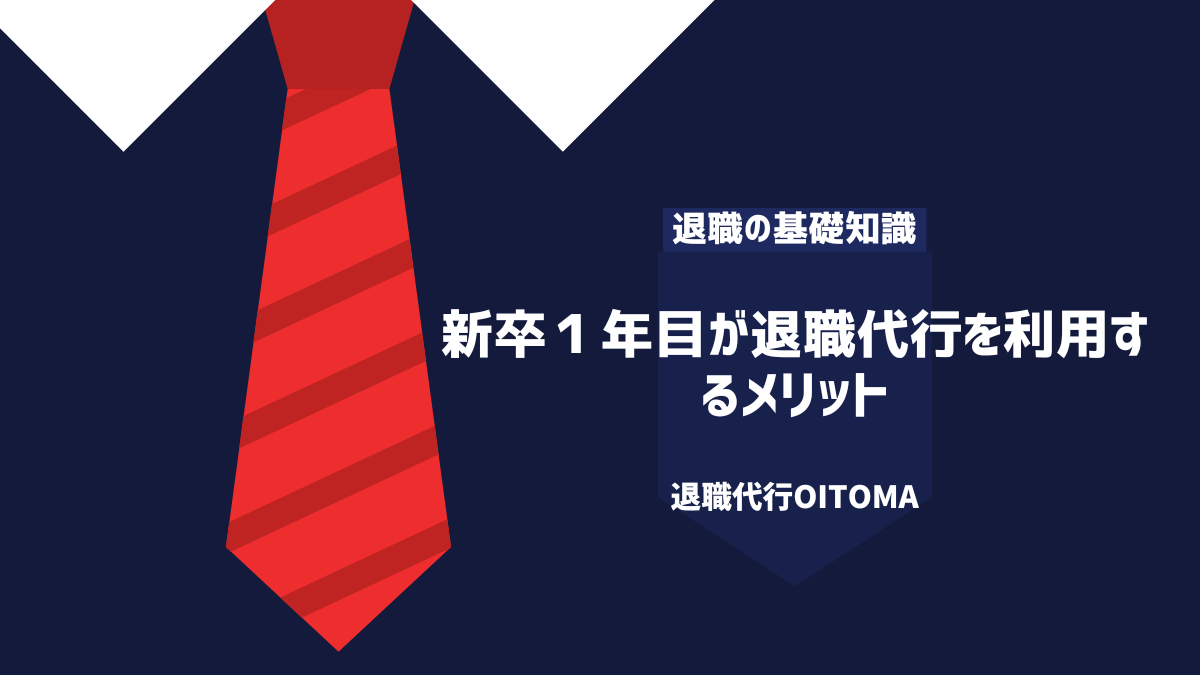
心理的負担の軽減
新卒1年目にとって、上司や人事に直接「辞めたい」と伝えるのは大きな心理的負担です。
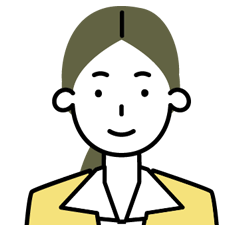 Aさん
Aさん
専門家によるサポート
退職代行サービスには、弁護士や社会保険労務士が関与している場合があります。
-
退職金の計算
-
有給休暇の取り扱い
-
社会保険の手続き
こうした 複雑な労務手続きも安心して任せられるのは、新卒には大きな安心材料です。
時間と労力の節約
退職は、退職届の作成・面談・引き継ぎ調整など意外と大変です。
 Bさん
Bさん
トラブル回避
よくあるトラブル例
-
退職を認めてもらえない
-
退職金を渋られる
-
引き継ぎを不当に長く要求される
新卒1年目は知識不足で不利になりがちですが、専門家が交渉をサポートすることで、スムーズに辞められる可能性が高まります。
新卒1年目が退職代行を利用するデメリット
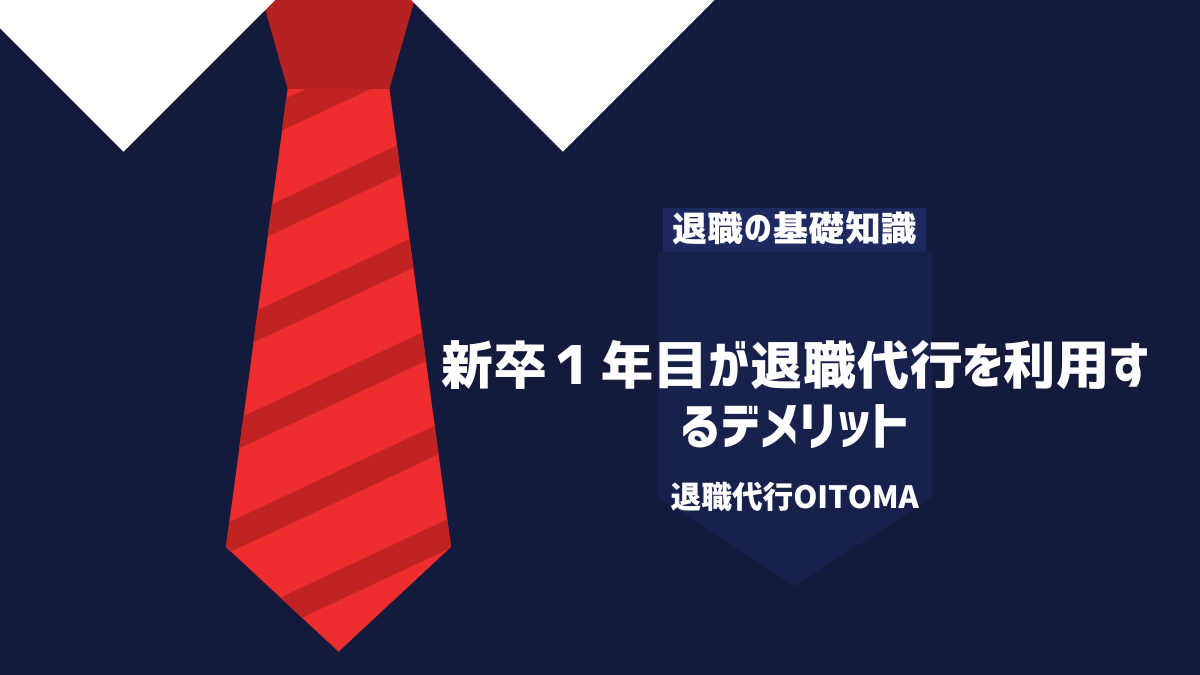
コストの問題
退職代行サービスの大きなデメリットのひとつは、費用がかかることです。
基本的なサービスでも 3万〜5万円 程度、新卒1年目の給与を考えると決して安くはありません。
 Uさん
Uさん
特に、低賃金や生活不安が理由で退職を考える人にとっては大きな負担になります。
また、法的支援付きプランでは 10万円以上かかるケースもあり、貯蓄が少ない新卒にとっては利用が難しい場合もあります。
経験不足による成長機会の喪失
退職代行を使うことで、自分で退職交渉をする経験を失うことになります。
これは本来、社会人として成長する貴重な機会でもあります。
-
困難な状況での交渉力
-
感情を抑えて話す自己コントロール力
-
上司に理由を伝える自己主張スキル
これらは将来のキャリアでも役立つスキルです。
退職代行を使えば楽に辞められますが、成長の機会を逃すリスクがある点は意識しておく必要があります。
将来のキャリアへの影響
新卒1年目の退職はまだ一般的ではなく、採用担当者から厳しく見られることもあります。
転職面接で聞かれやすい質問例
-
「なぜ1年で辞めたのですか?」
-
「なぜ直接交渉せず退職代行を利用したのですか?」
これらの質問に納得感のある答えを用意できないと、転職活動で不利になる可能性があります。
また、「退職代行を使った=コミュニケーション力や問題解決力が不足している」と受け取られるリスクもあります。
社会人としてのスキル未習得
新卒1年目は、社会人としての基礎を身につける大切な時期です。
-
ビジネスマナー
-
チームワーク
-
時間管理・ストレス管理
こうしたスキルは 職場経験を通じて学ぶものですが、早期退職によって十分に身につける機会を失う可能性があります。
その結果、次の職場で苦労したり、キャリア形成にハンデとなるリスクもあります。
信頼できる業者の選び方
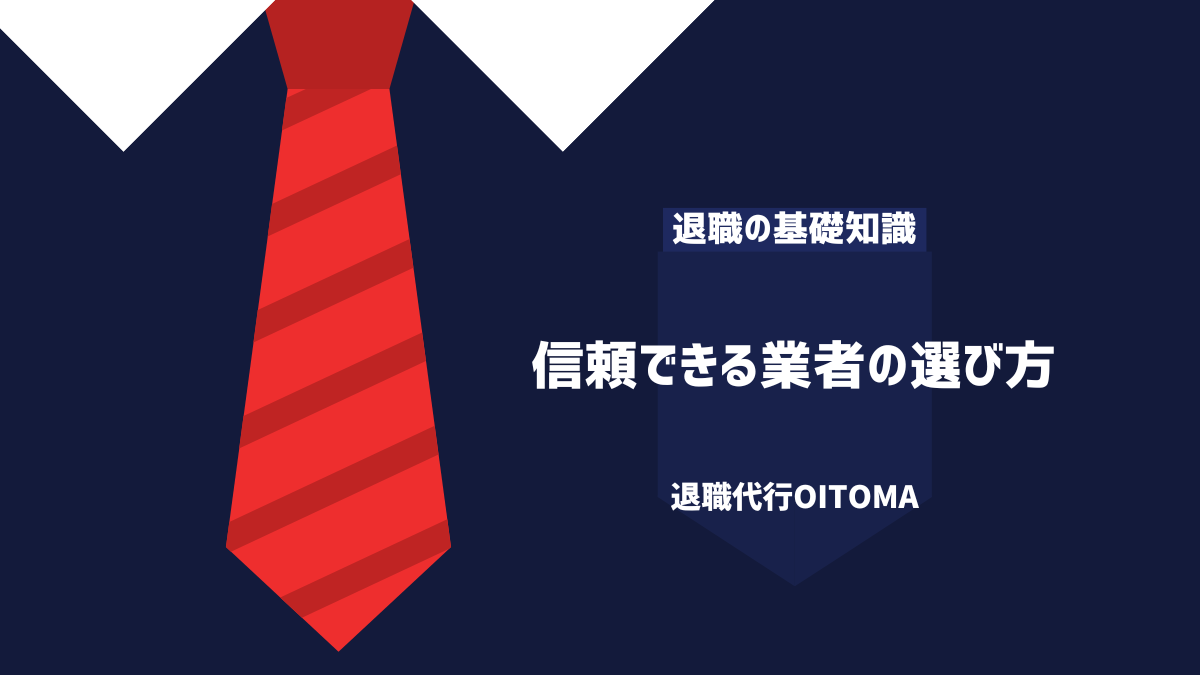
退職代行を使うなら、信頼性の見極めが最優先。
-
実績と評判:公式実績/第三者口コミを確認。ステマ臭の強いレビューは要注意。
-
専門家の関与:弁護士・社労士の監修や提携の有無。法的争点が絡むなら特に重要。
-
料金の透明性:総額・追加費用・返金条件が明記されているか。
-
連絡のスムーズさ:初回問い合わせのレス速度・説明の一貫性。
-
法令順守:脅し文句・違法な交渉宣言はNG。できること/できないことを明確に分けているか。
NG例
「即日100%辞められる保証」「会社と戦います」「追加費用は後で」などの煽り文句、
運営者情報や所在地が不明、契約書を出さない——こうした業者は避けましょう。
契約内容の確認
申し込む前に、書面で範囲と条件を把握しておくのが鉄則。
-
サービス範囲:連絡代行のみか、有給・退職金・備品返却まで含むか。
-
料金内訳:基本料金/オプション/追加費用の基準。
-
キャンセルポリシー:着手後の扱い、返金可否。
-
守秘義務:個人情報の保護と情報共有範囲。
-
保証の有無:連絡不達・会社未対応時の再実施や返金条件。
個人情報の取り扱い
利用時は個人情報を多く渡すため、方針を必ず確認。
-
利用目的の明確化:何のために、どの範囲で使うか。
-
第三者提供:どこに、どんな条件で共有されるか。
-
保管期間・廃棄:保有の期間と方法。
-
セキュリティ:アクセス権限・保管方法(暗号化等)。
退職後のフォローアップ
辞めた後の手続き・連絡まで見てくれるかで安心感が変わります。
-
公的手続きの案内:健康保険・年金・雇用保険など。
-
金銭面の確認:退職金/未払い賃金/精算のチェック。
-
会社からの問い合わせ対応:連絡窓口の継続期間。
-
証明書類:退職証明書・源泉徴収票の取得サポート。
新卒1年目が退職を決意する前に考えるべきこと
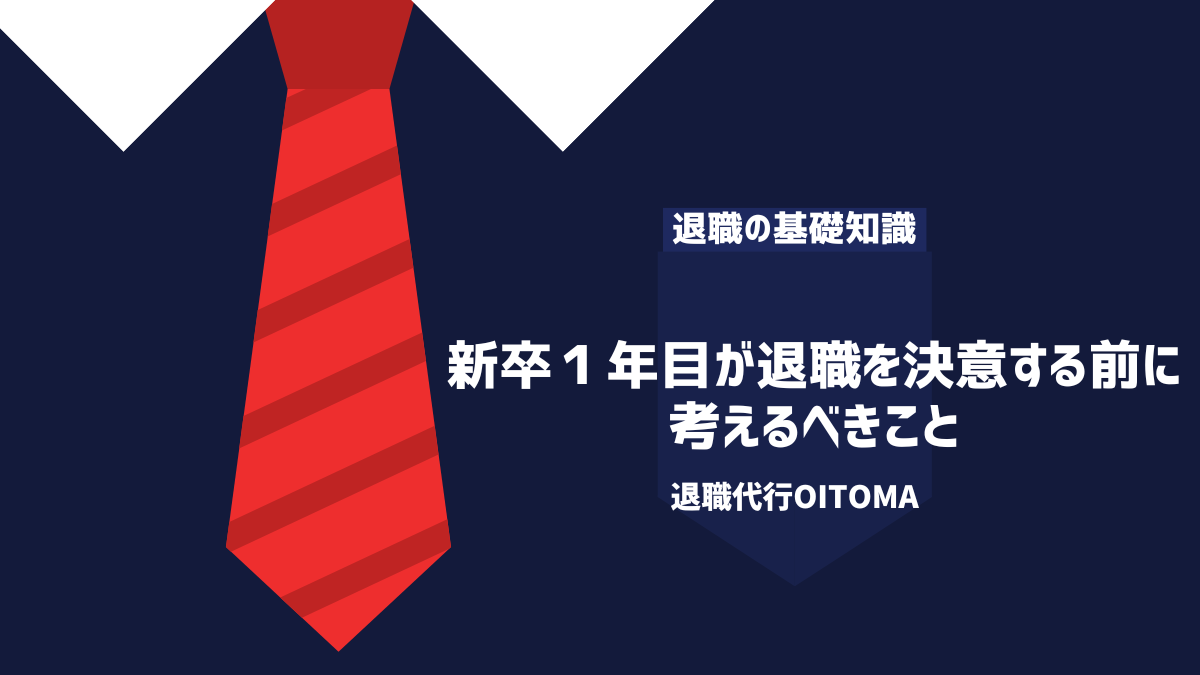
現状の正確な分析
まずはいま何がつらいのかを具体化しましょう。
-
理由の特定:何が嫌か(業務内容/人間関係/待遇/勤務地 など)を名詞で書き出す。
-
一時的か構造的か:繁忙期などの一時要因か、文化・体制など構造要因かを切り分ける。
-
自力で改善できるか:上司1on1・業務量調整依頼・担当変更など、自分発の打ち手を列挙。
-
会社の改善意思:提案→期限付きのアクションが出るかを確認。出なければ“体質”の可能性。
将来のキャリアプランの再考
長期のゴールに今の仕事がつながっているかを点検します。
-
目標との整合:3年後・5年後に“できるようになりたいこと”と現業務の接続。
-
業界/職種の再検討:他領域に強い興味や適性があるか。
-
成長余地:社内でスキルアップや資格の機会が確保できるか。
-
転職後の道筋:想定年収・働き方・必要スキル・次の次のキャリアまで描けるか。
社内での異動や配置転換の可能性
「会社は合っているが配属が合っていない」ケースを先に潰します。
-
正式ルートで相談:上司→人事の順で目的と根拠を添えて希望を伝える。
-
仮置き期限:○ヶ月待って変化がなければ次の選択肢へ進む基準を決める。
-
書面・ログ:面談メモやメールで合意事項を残す。
専門家(キャリアカウンセラー等)への相談
第三者の客観視点を入れると、決断の精度が上がります。
-
得られること:適性整理/職務経歴の棚卸し/求人市場の現実感。
-
相談先の例:大学キャリアセンター・自治体窓口・ハローワーク・民間キャリアコーチ・転職エージェント。
-
面談の持ち込み資料:職務メモ・強み弱み・希望条件(譲れない/譲れる)。
退職代行の代替案
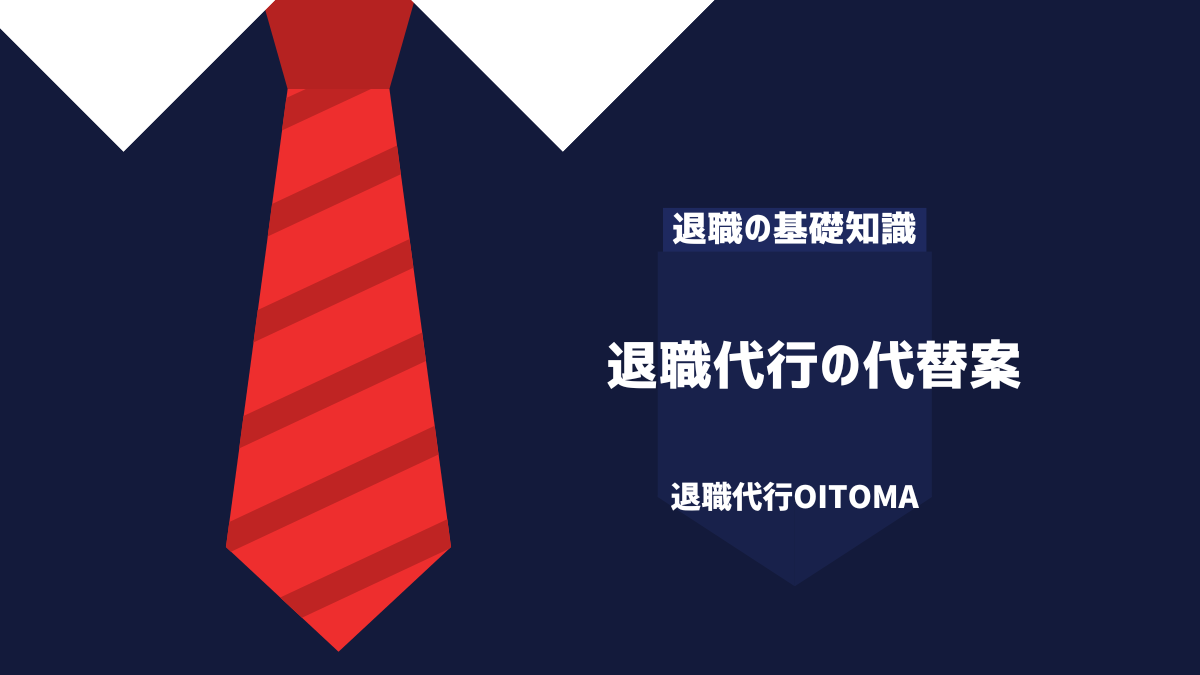
人事部門への相談
多くの企業には人事部門や相談窓口が設けられています。
-
制度・規則に精通しているため、配置転換・業務調整・メンタルケアなどの提案が可能
-
社員と会社の橋渡し役として機能
-
「退職一択」になる前に社内の改善策を模索できる
上司との直接交渉
退職理由を率直に伝える場を持つことで、意外な解決策が見つかることもあります。
-
誤解や行き違いを解消できる可能性
-
問題改善のための具体的な対策を上司が取れるケースも
-
良好な関係が築ければ、キャリア支援につながることも
労働組合の活用
労働組合がある会社なら強力な味方になります。
-
従業員の権利を守る立場で、会社との交渉力を持つ
-
労働条件改善・ハラスメント対応など、個人では難しい問題もサポート
-
「一人で闘わない」選択肢として有効
転職エージェントの利用
退職を視野に入れているなら、退職代行よりも転職エージェントを活用するのも手。
-
キャリア相談 → 求人紹介 → 内定までサポート
-
現職の課題を客観的に分析できる
-
次の就職先を決めてから退職できるため、経済的リスクを軽減
まとめ
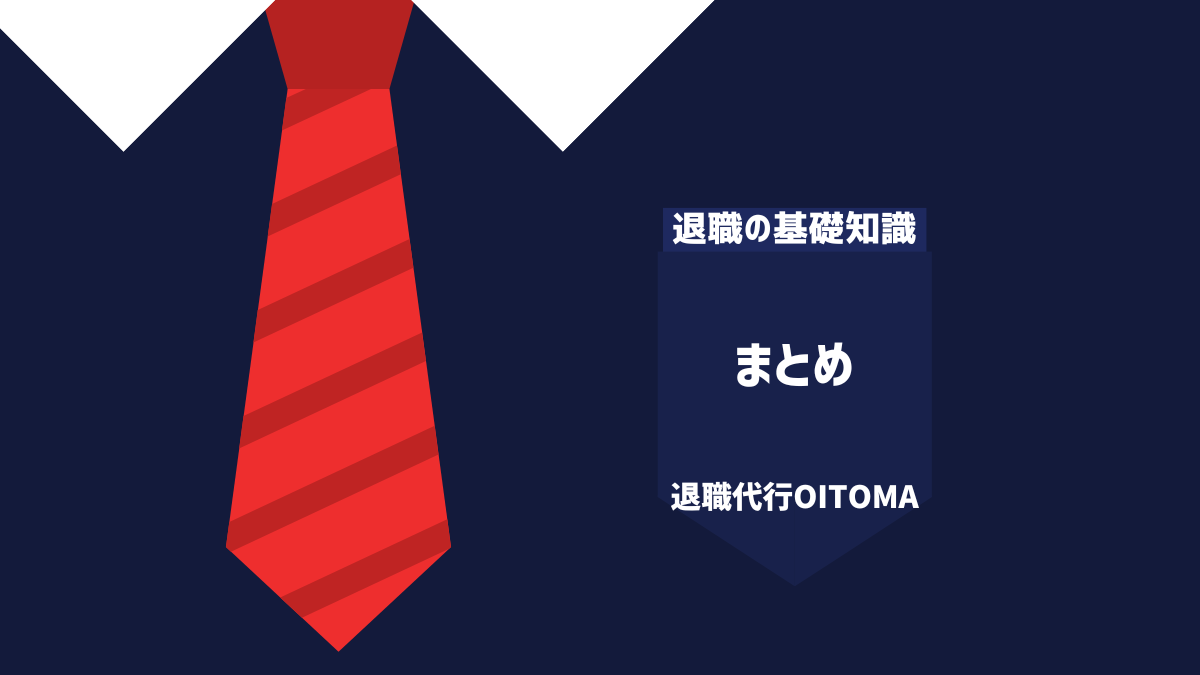
新卒1年目の退職は“大きな決断”。 退職代行はその一手段ですが、メリット/デメリットを両面で把握してから選ぶことが重要です。
メリット
- 心理的負担の軽減
- 専門家サポート
- 時間と労力の節約
- トラブル回避
デメリット
- コスト負担
- 交渉経験の喪失
- キャリアへの影響
- 社会人基礎スキルの未習得
決める前に、現状の正確な分析・キャリアの再設計・社内異動の検討・専門家相談を行い、人事相談/上司との対話/労組活用/転職エージェントなど代替手段も比較しましょう。
利用する場合は、信頼できる業者の選び方・契約内容・個人情報の取り扱い・退職後フォローを必ず確認。
短期のラクさだけでなく、長期のキャリア価値を基準に、十分な情報収集と熟考のうえで最善の選択を。
決断前最終ミニチェック
-
退職理由は具体名詞で明文化できた
-
一時要因/構造要因を切り分けた
-
社内で試せる打ち手を実施した(期限付き)
-
代替案(人事・上司・労組・転職支援)を検討した
- 退職代行を使うなら業者・契約・個人情報・フォローを確認した
よくある質問(FAQ)
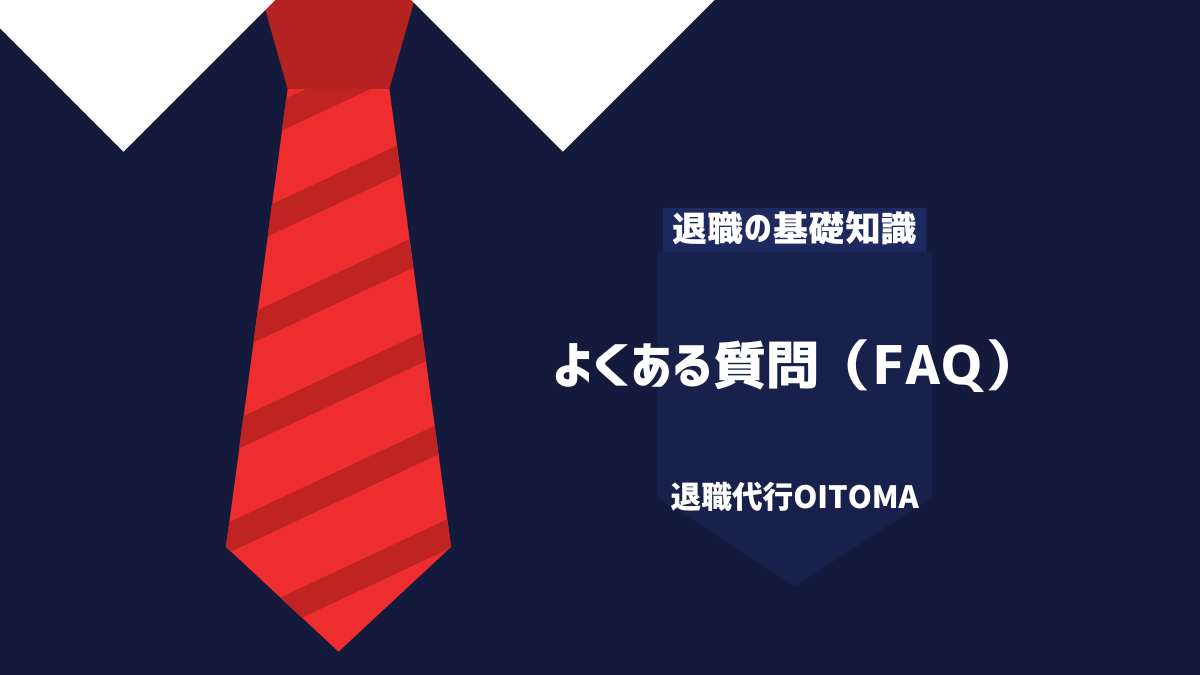
原則OK。
ただし脅迫・不当要求など違法行為はNG、交渉権限が必要な場面は弁護士関与が前提です。法令順守の業者を選びましょう。
直接の不利益は通常ありません。
ただし面接で「なぜ1年で退職?」「なぜ代行?」と問われることはあります。前向きな理由と学びを一貫して説明できる準備を。
一部の業者は応じることもありますが、基本は定額。
総額・追加費用・返金条件を見比べて複数社比較が安全です。
完全匿名は困難。
本人情報は会社に伝わりますが、対面や直接通話を避けることは可能です。
できるだけ早く業者へ連絡。
契約・進行状況次第でキャンセルや返金は条件次第。会社へ通知済みの撤回は難しい場合があります。
